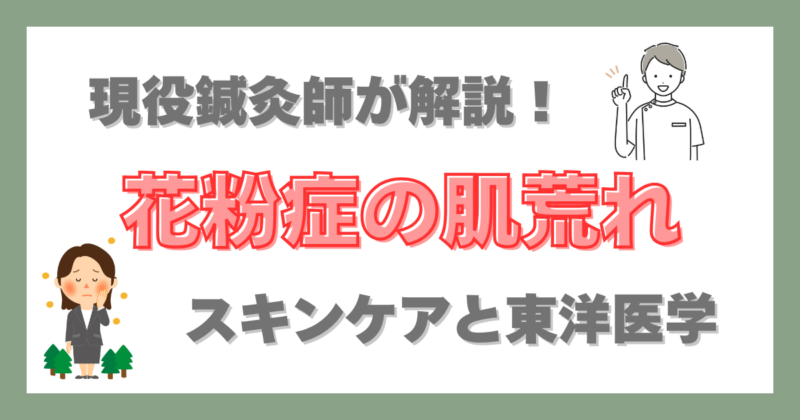春先になると、花粉症の症状に加えて「肌荒れ」に悩む方が増えます。
目や鼻のかゆみだけでなく、「顔が赤くなる」「肌がガサガサする」といった症状に心当たりはありませんか?
花粉症による肌荒れは、花粉の刺激だけでなく免疫反応や肌のバリア機能の低下が関与しています。
本記事では、花粉症による肌荒れのメカニズム、スキンケア、東洋医学的なアプローチなど詳しく解説。
花粉症による肌荒れのメカニズム
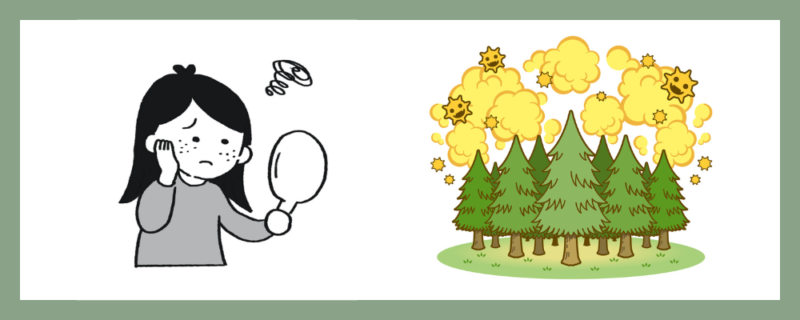
花粉症による肌荒れのメカニズムを詳しく解説していきます。
花粉の付着による直接的な刺激
春になると、大気中にはスギ・ヒノキなどの花粉が大量に飛散します。この花粉が顔や首、目元、鼻周りの肌に付着すると以下の影響を与えます。
乾燥肌や敏感肌の人はバリア機能が弱く、花粉の影響を受けやすい傾向。
肌のバリア機能低下
肌の表面には、外部の刺激から守る「バリア機能」があります。バリア機能が低下すると、肌は刺激を受けやすくなり炎症や乾燥が進行。
花粉の時期は気温や湿度の変化が激しく、皮脂の分泌バランスも乱れやすいため、バリア機能の低下が加速します。
花粉によるアレルギー反応
花粉症は、免疫システムが過剰に反応することで発症する疾患です。この免疫反応は肌にも影響を与え、以下の症状を引き起こします。
特に、肌のかゆみが強くなる原因は「ヒスタミン」です。アレルギー反応を引き起こす物質で、花粉が体内に入ると皮膚でも放出され、かゆみや赤みが悪化。
花粉症による肌荒れの悪化
花粉による肌荒れは、アレルギーとなる花粉の種類と飛散量に影響を受けます。スギ・ヒノキ花粉が多い時期(2月~4月)は、肌荒れの症状が特に強くなります。
花粉飛散量が多い日は要注意です。
晴れた日や風の強い日は、花粉が舞うことで肌に付着しやすく、雨上がりは、地面に落ちた花粉が乾燥して再び舞い上がります。
花粉が付着すると、目や鼻がムズムズして、つい手でこすってしまいがちです。この行動が肌荒れをさらに悪化させる原因になります。
肌の乾燥が進む
花粉症の季節は、気温の変化や湿度の低下も影響し、肌の乾燥が進みます。鼻水や涙で肌の水分が奪われ、乾燥によるかゆみ・粉吹きが悪化することも。
敏感肌の人は、乾燥による「敏感肌スパイラル」に注意が必要です。
皮脂の分泌バランスが乱れる
花粉の時期は、気温が変化することで皮脂の分泌が不安定になります。
「花粉ニキビ」は、花粉の付着と皮脂の酸化によって炎症が起きやすい状態です。脂性肌の人が花粉の影響を受けると起こりやすいので注意しましょう。
花粉症による肌荒れの原因は、単なる「花粉の付着」だけではありません。

免疫反応、バリア機能の低下、乾燥、皮脂バランスの乱れが関係しています。
花粉症による肌荒れを防ぐスキンケアと生活習慣

花粉の季節は、肌が敏感になり、かゆみ・赤み・乾燥・湿疹などのトラブルが起こりやすくなります。スキンケア・生活習慣・食事の視点から詳しく解説します。
肌のバリア機能を高める保湿ケア
花粉の影響で肌のバリア機能が低下すると、外部刺激を受けやすくなります。その結果、炎症が悪化しやすいため保湿が重要です。
保湿のポイント
肌に負担をかけない洗顔・クレンジング
花粉が肌に付着すると、肌荒れが起こりやすくなるため、洗顔でしっかり除去することが大切です。
洗顔のポイント
花粉を肌に付着させない工夫
外出時の対策
帰宅後のケア
生活習慣で肌トラブルを防ぐ
室内に花粉を持ち込まない工夫
ストレスを溜めない(自律神経のバランスを整える)
ストレスが増えると、交感神経が過剰に優位になり、肌の炎症やかゆみが悪化することがあります。
食事で肌の免疫バランスを整える
花粉症による肌荒れを防ぐために、抗炎症作用やバリア機能をサポートする栄養素を意識的に摂ることが重要です。
| 栄養素 | 効果 | 食品例 |
| ビタミンC | 抗酸化作用・免疫調整 | 赤ピーマン、ブロッコリー、レモン、キウイ |
| ビタミンE | 肌のバリア機能を高める | アーモンド、ひまわり油、カボチャ |
| オメガ3脂肪酸 | 抗炎症作用 | サバ、イワシ、アマニ油 |
| 亜鉛 | 皮膚の修復を助ける | 牡蠣、豚レバー、大豆製品 |
| ケルセチン | ヒスタミンの過剰分泌を抑える | 玉ねぎ、そば、ブロッコリー |
| 乳酸菌 | 腸内環境を整え、アレルギー症状を緩和 | ヨーグルト、ぬか漬け、キムチ |
東京大学の研究で、アレルギー性鼻炎による症状は「リノール酸」という脂質からでる成分が関わっていることがわかっています。
こちらの記事で解説していますので、ぜひご覧ください。
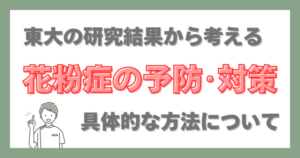
腸内環境を整える
腸内環境を整えることは、アレルギー症状の緩和につながるため、食物繊維や発酵食品を意識的に摂取しましょう。

バリア機能を守ること、花粉を身体に取り入れないこと、食事による免疫強化が大切です。
花粉症による肌荒れと東洋医学的アプローチ

「外邪(がいじゃ)」や「気血の巡り」といった考え方を基に、花粉症による肌荒れを改善する方法が用いられます。
鍼灸・食養生を中心に、東洋医学的なケアについて詳しく解説します。
花粉症による肌荒れの東洋医学的な捉え方
東洋医学では、肌荒れの原因を「内因(体質やストレス)」と「外因(花粉・乾燥などの環境要因)」のバランスの乱れと考えます。
花粉症による肌荒れは、以下の3つの要素が関係しているとされます。
風邪(ふうじゃ)による刺激
「風邪(ふうじゃ)」は、東洋医学で外部からの影響(花粉・ホコリ・乾燥など)を指します。
風邪が皮膚に影響を与えると、かゆみ・赤み・乾燥などの症状が現れます。
肺の不調とバリア機能の低下
東洋医学では、「肺は皮毛(ひもう)を主る」と言われ、肺の働きが肌の健康に関与すると考えます。
花粉症による鼻炎や咳が続くと、肺の機能が低下して肌のバリア機能も低下する可能性があります。
気血水の乱れ
「気(エネルギー)」、「血(栄養)」、「水(体液)」のバランスが崩れると、肌のターンオーバーが乱れ、乾燥や吹き出物が起こりやすくなります。
ストレスや睡眠不足は「気血の巡り」を悪くし、肌荒れを引き起こす原因になります。
鍼灸によるアプローチ
鍼灸は、気血の巡りを整え、免疫バランスを調整することで、花粉症による肌荒れの改善が期待されます。特に以下の効果が考えられます。
花粉症に対する鍼治療に関して、こちらの記事で詳しく説明しています。ぜひご覧ください。
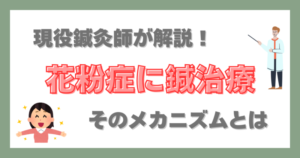
花粉症による肌荒れにおすすめのツボ
| ツボ名 | 位置 | 期待できる効果 |
| 合谷(ごうこく) | 手の甲、親指と人差し指の間 | 炎症を抑え、免疫バランスを整える |
| 曲池(きょくち) | 肘を曲げたときにできるシワの外側 | 肌の調子を整え、アレルギー症状を緩和 |
| 肺兪(はいゆ) | 背中の肩甲骨付近 | 肺の機能を高め、バリア機能をサポート |
| 血海(けっかい) | 膝の内側、膝蓋骨(しつがいこつ)の上方 | 血流を促進し、肌のターンオーバーを正常化 |
| 陰陵泉(いんりょうせん) | すねの内側、膝下 | 水分代謝を整え、乾燥肌を防ぐ |
これらのツボを1日数回、優しく5〜10秒ほど押すことで、肌の調子を整えるのに役立ちます。
食養生(東洋医学的な食事ケア)
花粉症による肌荒れを防ぐ可能性のある食材。
| 食材 | 期待される作用 |
| 緑茶・甜茶 | 抗ヒスタミン作用を持ち、炎症を抑える |
| レンコン | 粘膜を保護し、アレルギー症状を和らげる |
| 大豆製品(納豆・豆腐) | 腸内環境を整え、免疫バランスを調整 |
| くるみ・アーモンド | 必須脂肪酸が肌の乾燥を防ぐ |
| 根菜類(にんじん・ごぼう) | 胃腸を温め、肌の調子を整える |
東洋医学では、花粉症による肌荒れは「風邪の影響」「肺の不調」「気血の乱れ」が関係していると考えられます。

鍼灸・漢方・食養生を組み合わせることで、免疫のバランスを整え、肌のバリア機能を高めることが重要です。
まとめ

花粉症シーズンの肌荒れ対策として、日々のスキンケアや食事、鍼灸を取り入れてみませんか?
あなたの肌を守るための一歩を、今日から始めましょう!

最後までご覧いただきありがとうございます。
本記事が少しでも皆さまの参考になると嬉しい限りです!